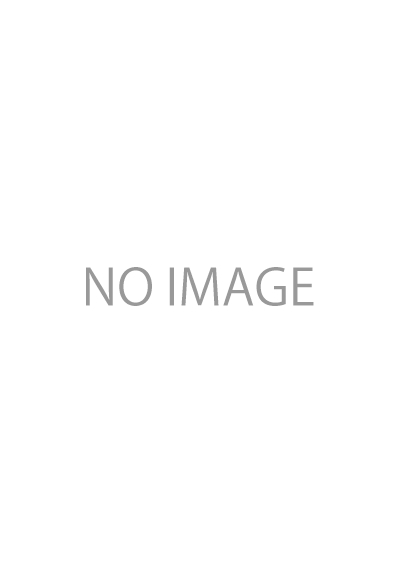
- 販売終了
J-VET 2008年3月号 離断性骨軟骨症の診断と治療 COMPENDIUM:犬の難産 他
最新獣医学エビデンス情報誌 月刊「J-VET」
小動物診療のエビデンスわが国獣医療界にもEBM(Evidence Based Medicine)を。
■臨床現場でよくみる疾患や症状について,現時点のエビデンスを掲載しています。
■日本の執筆陣が,日本の獣医療の実情をふまえて執筆しているため,飼い主へのインフォームドコンセントにもすぐに役立ちます。COMPENDIUM世界レベルの記事を日本語訳で。
■世界各国で最も信頼されている獣医学雑誌から,わが国獣医療界の臨床事情に鑑み,重要と考えられる記事をピックアップし,掲載しています。
■オリジナル発行後約6カ月で日本語訳を掲載。日常診療でよくみる疾患、まれにしかみない疾患の知識をアップデートできます。
ご注文はこちら
- 目次
-
■小動物診療のエビデンス
■整形外科疾患のエビデンス5
離断性骨軟骨症の診断と治療
藤木 誠
離断性骨軟骨症の病態を理解することは,診断およびその治療に必要である。単純X線検査,およびCT検査,関節鏡検査などの画像検査を組み合わせて行うことで,治療に役立つ正確な診断が可能となる。なかでも関節鏡は診断と治療の両者において効果的な方法である。軟骨病変を早期に検出することと,適切な治療により関節軟骨を保護すること,そして続発する二次的な骨病変の進行を防止することが予後に大きく影響する。
■COMPENDIUM
■犬の難産:内科,外科
監訳:瀬戸口明日香
難産は,犬ではよく起こる緊急事態である。臨床獣医師は迅速に分娩期を判断し,処置が必要か否かを決定しなくてはならない。難産の診断と管理は,身体検査,膣検査,腹部X線検査,腹部超音波検査,胎子の心拍数,子宮内圧が手がかりとなる。内科的管理の主体は,オキシトシンの投与,静脈輸液,グルコン酸カルシウムの投与である。しかしながら,難産症例のおよそ62%は外科処置が必要となる。出産直前の母犬と新生子の特殊な生理状態に適した麻酔を施し,適切なタイミングで外科処置を行うことにより,子犬の死亡率(22%)と母犬の死亡率(1%)を低下させることができるであろう。
進化するインスリン療法
監訳:西飯直仁
市販されているインスリン製剤は,ヒトの糖尿病においてより効果的で副作用の少ない治療薬にしようという努力の結果,長い年月をかけて進化してきた。獣医師は,インスリン製剤が入手可能かどうかによってインスリンを選択しなければならない。最初のインスリン製剤は動物由来のものであったが,科学技術が進歩し,抗インスリン抗体の産生を防ぐためのヒト遺伝子組換えインスリンが開発された。近年のインスリンアナログの出現によってヒトのインスリン市場の需要に変化がもたらされ,獣医師もこれに従わざるをえなくなった。本稿は,獣医療において利用可能なインスリン製剤の手引きである。
■UK VET
■犬の尿失禁1. 診断
翻訳:村田裕史
尿失禁とは,蓄尿期における不随意な尿の排泄をいう。これは犬ではよくみられ,飼い主や動物自身に重大な問題を引き起こす。多くの疾患が尿失禁の原因となることから,適切な治療を行って予後を良化するためには,適切な診断的検査を行うことが必須である。本稿は蓄尿と排尿の病態生理と診断法を概説する
■連載,他
■犬と猫の臨床腫瘍学 第3回 画像診断と生検
森崇
腫瘍性疾患の治療プランを立てるにあたって,画像診断と生検は避けて通ることができない。さまざまな画像診断法や生検法の長所と短所,組み合わせ方を知っておく必要がある。
第11回岐阜大学教育セミナー
教育講演犬のリンパ腫 ― 診断のための検査法の特徴 ―
大場恵典
犬のリンパ腫の検査法を解説する。細胞診,病理組織検査,フローサイトメトリー,近年話題になっているクローナリティー解析について,各検査の目的および特徴と相違点を述べる。
画像診断シリーズ 実践 心エコー検査(第2部)
エコー検査所見に応じた確定診断法とその治療(3)
右心房のモザイク
田中綾
右心系の異常は症状が出にくいのが特徴である。臨床症状やX線検査による病態評価が難しく,心エコーによる病態評価が適切に行われることが重要視される。今回は右心房にモザイクパターンが現れる疾患を解説する。
小動物歯科シリーズ 基礎からの小動物歯科学 第16回
口臭を考える
藤田桂一
今回は少し趣向を変えて口臭を取り上げる。口腔疾患において最も多い主訴は口臭ではなかろうか。生理的口臭か異常な口臭かを判断し,発生機序をたどることにより,隠れた疾患を見出せることもある。カナダ Saskatchewan大学 放射線腫瘍科のインターン
吉川陽人
- 商品情報
-
- 商品ID
- 00010803
- 判型
- A4
- 発刊日
- 2008年3月10日

